★第4の神話
篠田節子 角川書店 1999.11
森瑤子をモデルにした小説だとどこかにあり、興味がわいた。
最近、再び森瑤子について考えさせられる機会があり、それもあって。
篠田さんは数冊しか読んでいないけれど、
女性の描き方や、一気読みさせるグルーブ感が好きな作家である。
これも一気読みした。
一気読みしたのに物足りなかったのは、たぶん私が森瑤子を下敷きにして読んだからで、
森瑤子を知らない人が読めば、そんなこともないのかもしれない。
 4年前に亡くなった夏木柚香は、華やかな「神話」に彩られたベストセラー作家だった。フリーライターの小山田万智子は、雑誌に彼女についての「第二の神話」 を書くことを依頼される。記事は評判となった。だが、取材を通して見えてきた作家の姿は、それまでの「神話」とは異なるものであった。こうして「第三の神話」が立ち上がってくるが、その向うには更に別の神話(あるいは真実)があった…。
4年前に亡くなった夏木柚香は、華やかな「神話」に彩られたベストセラー作家だった。フリーライターの小山田万智子は、雑誌に彼女についての「第二の神話」 を書くことを依頼される。記事は評判となった。だが、取材を通して見えてきた作家の姿は、それまでの「神話」とは異なるものであった。こうして「第三の神話」が立ち上がってくるが、その向うには更に別の神話(あるいは真実)があった…。
謎がある。ずれがある。何かが引っかかる。ゴーストライ ターで終わりたくない万智子に、夏木柚香のドキュメントを書いてみたいという野心が育っていく。自分の名前入りの「本」を書くのだ。その野心だけでなく、 謎やずれや引っかかりに誘われるように、出版されるめどもないまま、万智子は取材を重ねていく。
謎やずれや引っ掛かりはそれなりにクリアにされていき、と思いきや更にそれがひっくり返されたりして、すらすらさらさらどしどしと読んでしまう。が読み終わった後、(森瑤子を下敷きにしているせいか)どうもすっきりしない。
誰もが羨み、あこがれ、誰からも愛されるような夏木柚香というイメージとは裏腹に、彼女が抱えていた「壮絶な孤独」や「歪んだ夫婦関係」は、謎やずれや引っ かかりというよりも、言葉にしてしまえば「そういうこともあるだろうな」という程度のことで、深い感情移入をもたらさない。最後に、それまでの三つの神話を超えるものとして肯定的に描かれる短編小説『夕凪』をめぐる顛末も、先が読める安易な展開で書き込みが足りなく、クライマックス感もなく終わってしまう。
中段で万智子は夏木柚香の作品を、「作者のライフスタイルに依存してしか、人気を勝ち取ることのできない作品の悲しさ」と、評してい る。その後万智子は他の作品を読み込む中で、そうではない作品も見出し、それが「第四の神話」に繋がっていくのだが、その「本格的な作品」がまた魅力に乏しい。
「本格的な作品」の実があまりないのに比して、「作者のライフスタイルに依存した作品」という批判にはリアリティがある。柚香のライフスタイルと正反対の暮らしをしている万智子には、旅先の優雅なリゾート地を、アヴァンチュールの舞台としてしか描けない作家の視点が腹立たしい。万智子は観光客や恋人たちが見ようとしない世界にも、思いが至るライターなのだ。
そんな万智子が、柚香の何に惹かれたのだろう。第二、第三、第四 の「神話」までも仕掛けようとする出版社の藤堂喜代子は、柚香にほれ込んでいた。仕掛けは死の床で柚香と約束されたものであり、その約束を藤堂はビジネスを超えて果たそうとする。ではその魅力とは何か。いずれもよくわからないのだ。
ネックはやはり、核となる女性作家夏木柚香の造形がイマイチなことだろう。力が入っているのは万智子。篠田さんはおそらく、万智子のようなありかたには肩入れできるけれど、夏木柚香のようなありかたにはノレない(のり移れない)のだ。
森瑤子は一世を風靡した作家である。彼女の作品群は、いかにそこに量産による筆の荒れがあったにしても、誰にでも簡単に書けるようなものではない。ライフスタイルの(作品と一体となった)商品化も、自己プロデュースにしても同様である。いずれも出版社の仕掛けだけで為されたわけではない。それだけでなく、作家とその作品があれほど熱狂的に支持された意味というものは、歴然とある。
同年代及び少し下の世代の女性に森瑤子の名前を出すと、実にたくさんの人が、あの頃はよく読んだ、懐かしい、好きだった、あこがれた、と答える。そして、でももう今は読まない。遠ざかってしまった、というように続ける。私のように(好きな三冊に関しては)今もって読み返すようなのは少数派だ。森瑤子は消費されてしまったのだ。
では本当に、森瑤子はそれだけの「懐かしい」「あの頃」の作家なのだろうか。そうではない、と篠田さんは夏木柚香を書いた。のだけれど…。
森瑤子を(モデルに)書きたいというのはわかる。頂点があって凋落があり、裏側のドラマもある。様々なネタにあふれている。何層かの異なったイメージの重なりがあって、それを暴いていくプロットを立てやすい。でも、あらかたの「謎」や「ずれ」はすでに世間に流布してしまっている。小説にするには、世間並みの解明では足りない。
なによりも作家として、女性として、彼女をどう評価し、あるいはしないのか。この本には、その部分が足りないような気がする。リアリティのある万智子の(当初の)否定的な視点に徹底的にこだわるのも、ひとつの手だったのではないか。いや、プロットはそうなってるんだけど…。つまり中途半端ってことか。
そしてもう一つ。このような作家や作品は、決して個人の特殊な資質や奇異な関係性だけで生まれるわけ ではない、ということ。このような作家と作品を生んだ時代の必然があり、それが否定される時代の必然がある。柚香と万智子の間にある時代の大きな隔絶と転換、そこを繋ごうとする死の床の柚香と藤堂の思惑とその後の格闘、それに万智子がどう巻き込まれ、どう自分のものとして取り込んでいくのか。
小説として森瑤子を書くのなら、夏木柚香を現実の森瑤子を超えるほどの圧倒的な迫力で造形しなければいけない、ということがあるけれど、もうひとつ、柚香と万智子のつながり、万智子が柚香から継承する何かを作り出せなければ、小説としては弱い。
森瑤子はその総体が作品だった。柚香が目指した「総合芸術」は、森瑤子にあっては生身の、かつ作家である「森瑤子」としてしか結実しないものであった。とすれば森瑤子を書くのなら、それは小説ではなく、ドキュメンタリー、あるいは評伝のほうがよかったのかもしれない。
瀬戸内晴美の『かの子繚乱』を思い出している。
【付】
篠田さんの作品では『仮想儀礼』がすごい。
あれくらいのボリュームがあったらまた違ったかもしれないね。
【付2】
検索していたら、
森瑤子 a tribute to a handsome woman
というサイトを見つけた。
森さんの娘さん(たち?)が管理しているサイトのようだ。
ここに、昨年三冊が復刊されたことと、「望郷」が重版されたとのニュースがあった。NHKドラマ「マッサン」と同じモデルを元に書かれた「望郷」が、注目されたのだろう。復刊三冊のなかに『夜ごとの揺り籠、舟、あるいは戦場』が入っていたのが嬉しかった。




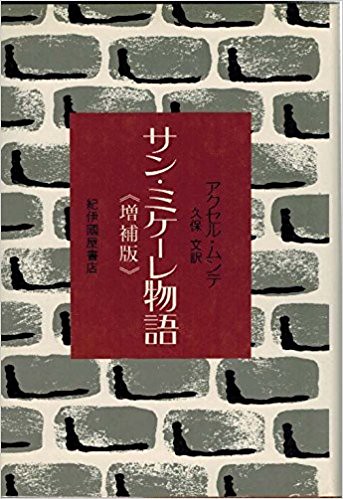





コメント