カリフ制と言われても、まったくピンと来ない。
だいたいカリフとイマムとスルタンという呼称でも混乱する。
これまで読み拾った知識を整理してみると…、
カリフはイスラム共同体の最高指導者でスンニ派の呼称、
シーア派ではイマムと呼ぶ、という解釈で良さそう。
ゆえにカリフ制再興を掲げるのはスンニ派のみ。
スルタンは、宗教指導者ではなくて政治的トップ、
イスラム国家の王というのがしっくりくるようだ。
で、あらためて、カリフ制ってなんなんだろう ?
初期イスラム共同体では、ムハンマドの死後、彼に付き従ってきた信奉者や親族の中から四名の後継者が順次指導者として選任され、共同体の維持と拡大に力を尽くした。
この四人が元祖カリフであるが、以後はカリフ(後継者)を選任とするか、ムハンマドの血統で世襲とするかでスンニ派とシーア派に分裂し、今に至る。また、この時代を正統カリフ時代と呼び、以後の王朝時代 ? のカリフとを区別している。
カリフの権限については、正統カリフ時代には宗教的権威ではなく政治的指導者であったものが、以後宗教的権限も持つようになった。
10-11世紀の王朝では、スルタンがカリフの後ろ盾のような力を持つようになり、その後カリフを傀儡としたり、廃位したり。
オスマン帝国ではカリフが復位されるも、スルタンがカリフも名乗るようになり、象徴的意味あいだけが残っていた。
オスマントルコの崩壊後、近代トルコ建国にあたり、アタチュルクによってスルタンともどもカリフも廃止(1924年)となった。
両世界大戦のあと、かつてのイスラム共同体は分断され、いくつかの国家となり、それぞれの地域にそれぞれの政治体制による問題や紛争が出現し、かつての共同体の栄光は失われてしまった。
イスラムの人たちがイスラム共同体の統合を、イスラムの歴史的な観点からも、イスラムの教えの観点からも求める気持ちは理解できる。
日本でカリフ制再興をうったえているイスラム学者中田考氏は、イスラムという宗教の下、共通する言語、法、心性、慣習をもつ、モロッコからインドネシアに至る人々がこれほど分裂してしまったのは、カリフ制が廃止されてしまったからだ、という。つまり、イスラム共同体の統合原理であったイスラーム聖法(シャーリアの諸規範)を放棄し、西洋の法典および統治制度を採用したことにより、イスラム共同体のまとまりは失われてしまったのだ、と。
イスラム世界では、政治改革や社会改革の折り目に、イスラム回帰、あるいはイスラム復興運動が起きる。エジプト2011年のモスリム同胞団の躍進もこの流れだと思う。ではカリフ制再興も、イスラム復興運動の一つ、あるいは究極のイスラム復興運動なのだろうか。
また、そのカリフ制のカリフは、いったいどの時代のカリフなのだろう。政治的権限だけを持つ正統派時代のカリフなのか、それとも宗教的権威と政治的権威を併せ持つカリフか、それとも、日本の天皇のような象徴的権威なのか。
中田考氏の講演録を読んだ。
イスラームの今日的使命 : カリフ制再興による大地の解放
「理念形」としてのカリフ制は、(1)イスラム法により(2)イスラム共同体から選任されたカリフ(元首)の下、(3)支配に服する全ての領域が単一の法によって治められる。また(4)政令は、民選の諮問議会により作成されるも元首の裁可によって施行される。これが4原則だという。
中田氏は特に(3)の単一制が、西欧政治思想の国家主権の単一性と同じものではない、「欧米の政治思想の核心は、領域国民国家イデオロギーであり、イスラーム政体の第三原則はそれを真っ向から否定するものだ」と言う。
欧米人は自分たちが自由と人権を尊ぶ民主主義者だと考えていますが、それはそれで必ずしも誤りとは言い切れないとしても、自由や人権や民主主義はお飾りとは言わなくともあくまでも従属的であって、本当のところは彼らの最高の価値観は領域国家イデオロギーです。ですから、少数民族、あるいはエスニシティーにしろ、地域にしろ、民族にしろ、その他のいかなる思想、信条にしろ、国籍以外の帰属に基づくマイノリティーグループが、彼らが自分たちの集団の中で民主的に独立を決定して、独立を訴えても、決して独立を認めません。・・・つまり、領域国民国家のイデオロギーと、民主主義や人権などの価値の二者択一を迫られた時、欧米人が選ぶのは領域国家イデオロギーなのです。
政体を支配者の数が単独か、少数者か、多数者かで分類するギリシャの政治思想の伝統に呪縛され、支配者の数に偏執的に拘る西欧人は、カリフ制と聞くと、単独者の支配する独裁制を思い浮かべるようです。本質を見損なう愚かな反応と言わざるを得ません。カリフ制とは、なによりも、地球全体、人類全体を、神の法(シャリーア)の支配の下におこうとの、真の意味でのグローバリゼーションの政治思想なのです。
中田氏の他の論考なども参照すると、(たとえば『スンナ派カリフ論の脱構築 : 地上における法の支配の実現』など)カリフがただ一人でなければいけないというのは、統一なったイスラム共同体の象徴として、ということのようだ。
氏の言うカリフ制と、先日イラクで建国宣言したIS(「イスラム国」)のカリフ国がどこまで理念として重なるのかは不明だ。
また、西はモロッコやセネガルから東はインドネシアまで広がる16億人超を擁する地域がひとつのカリフをいただく国家となるというのは、あまりに壮大な構想だし、即座にいくつもの素朴なクエスチョンが浮かぶ。
例えば、カリフの正統な選任をどう行うのか。ローマ法王選出は、カトリック聖職者ヒエラルキーのトップ集団である枢機卿が世界中からバチカンはシスティーナ礼拝堂に集まり、閉じこもり、この枢機卿の中からコンクラーベという選挙で法王を選出する。でも、聖職者がいないイスラムでは聖職者組織も無いんだよね、確か、とか(法学者についてはよく知らない)。
あるいは、イスラム法統治の象徴的な存在がカリフだとして、じゃあ政治指導者はどう選ぶのか、とか。
あるいは、イスラムは他の宗教信徒や無宗教者にイスラムを強要はしない。異教徒もジズヤ(人頭税)を払えば共存が可能だし、社会活動は経済だけでなく政治的にも平等に行える。イスラムの基本となる刑法や商法は守る必要があるが、各宗教団体やコミュニティーでは、彼らの慣習的な法律、例えば婚姻や家族にかかわるものは独自に制定できる。このように中田氏はイスラム・カリフ制の多元性を強調するけれど、でもやっぱり非ムスリムは二級市民だよなあたぶん、とか。
つまるところ、ネックはイスラム法なんだと思う。
聖と俗の分化を基調とするヨーロッパ・キリスト教文明は、俗なる領域である政治と、聖なる領域である宗教の分離には偏執的にこだわる傾向があります。一方、法と政治が別の領域であるとの自覚が薄いため、既に述べたように為政者の命令に過ぎない立法府の制定した「法律」と、社会の起源と同じほど古くから妥当するものとして社会の全ての成員が承知しているものと考えられている「法」とを区別することができません。また合理的に体系化された行為規範の束である法体系と、理性を超えた超越的存在との象徴的コミュニケーションの体系である宗教が別の領域であることも十分に理解できていません。
これはどういうことなのだろう。
イスラムは聖俗をキリスト教社会のように「偏執的」に分けてはいない、ということは、イスラム法シャリーアの法源とされるクルアーン(コーラン)やハディース(ムハンマドの言行録)は聖典でもあり法典でもあるということだ。それでもイスラムの人たちは、「合理的に体系化された行為規範の束である法体系と、理性を超えた超越的存在との象徴的コミュニケーションの体系である宗教が別の領域」であると認識しているのだろうか。
つまり、クルアーンやハディースは、聖典として読むときは宗教書であり、法典として読むときは法体系となるから、読む主体、あるいは行為する主体にとっては両者は厳然と分かたれている、ということだろうか。これはまた、宗教の部分はムスリムに対してのみ適用され、合理的な法体系は非ムスリムを含む全員に適用される、ということでもあるのだろうか。いや解りにくい。
カリフ制においては非ムスリムは宗教であるイスラムを強要されなくともイスラム法は強要されるわけだし、そのなかで聖と法は「偏執的に」わかれていないにもかかわらず別の領域なのだと言われても、困惑するばかりだ。それに、「イスラム法は合理的な法体系」と言われても、合理的なものもそうでないものがまざってるように思えるし。
たとえば食物禁忌。当初は禁忌とする何らかの合理性や明確な理由があったのだと思うけれど、それは時代と共に失われているのではないだろうか(不可侵の宗教規範としてはそれでもいいんだけれど)。
また女性の権利については、あきらかに現実にそぐわなくなっている。四人の妻がOKなら四人の夫もOKなのでは ? 美しいところを隠すベールは、女性だけなく男性にも必要なのでは ? 車の運転などの規制はもちろん容認できない。
カリフ制の第一原則として外せないイスラム法の下にイスラム共同体がまとまっていくのはいいとして、そのカリフ制がオルタナティブな政治イデオロギーとして、数の論理ではなくひとつの理念として認知されるには、どうしても決定的に引っかかる部分があるように思えてしまう。ただしこれは、イスラム法の無謬性に触れる、難しい、けれども根源的な課題のように思う。
イスラムが短期間に広い地域に広まったこと、そしてそれが今に至るまでしっかりと生き残っているということには、きっと大きな理由があるのだろうと思う。イスラムに宗教改革がなかったわけでもない。それがキリスト教のように既成の権威を疑い、否定し、その後ルネッサンスと呼応しあって近代科学の発展に繋がるような動きにならならなかったのにも、きっと理由があるのだ。例えば、イスラムにはヨーロッパ中世の異端審問のような宗教的抑圧は無かったことからも、改革を求める必要のないほど完成し安定した聖・法体系を持っていたからだ、とも言える。
でも、やはり、時代は動いていく。フェミニズムからイスラムを見直す動きもあって、それによると、イスラムはもともと女性差別的な宗教ではないという。イスラム法が確立した12-13世紀(から近現代)までの時代的、地域的な父権制が反映されているのだ、ということらしい。
さて、カリフ制について、上記のような問いをとりあえずは脇に置いてみると、経済圏としてだけでも、EUをはるかにしのぐイスラム圏が可能になる。
すでに共通の聖・法典(の原型)があり、それによる慣習文化があり、グローバルにヒト・カネ・モノが動くときに最も大きな道具となる共通の言語がある。この広大なイスラム圏が平和で安定した、かつ公平で自由な世界であるのなら、確かにオルタナティブな政治イデオロギーになり得るのかもしれない。中田氏の言う「領域国民国家イデオロギー」が暴力的な欺瞞性と二重基準で国家を構築維持拡大し、そこに多くの犠牲が悲劇的に捧げられてきた(今もいる)ことは確かだからだ。
欧米でも日本でもイスラムは多く誤解されるか、よくわからないものと遠ざけられてきた。私たちは、イスラム人口が世界の三分の一に迫ろうとしているにもかかわらず、宗教だけでなく彼らの歴史信条や現実をも見ようとしてこなかった。イスラムにも、そのように理解を促すアプローチが不足していた、ということもあったかもしれない。
けれどもこうやって見回してみると、中田氏だけでなく、イスラムに関する多くの論考や著作が日本語で読める。私たちにはキリスト教社会と違って、彼らと争ったこともない。キリスト教社会が持っている固定的なイスラムのイメージを捨ててみれば、そこには私たち日本人にとってよりシンパシーを感じるイスラムの心情や慣習もある。それに加えて、人間が便宜的に定めた国や民族や宗教の垣根を超えて共存できる共同体という可能性を、カリフ制は垣間見せてくれるように思う。
争いのロジックではなく、
平和共存のロジックとしてのオルタナティブに期待しつつ。
(※アイキャッチ画像のアラビア文字はサラーム、平和という意味)
付記 8/14
朝日中東ジャーナルの記事を読んだ。
1920年代、つまりサイクス・ピコ協定で中東が分割される時期、また、トルコにおけるカリフ制の廃止を挟む時期のカリフ制再興運動から説き起こし、その後のカリフ制論の盛衰と、アラブの国民国家の成熟とを視座に入れた論考。
アラブの春、イスラム復興運動としてのエジプトのモスリム同胞団の活動、「カリフ国(IS)」宣言まで、中東の大きな、うねる、「国民統合のあり方を改めて問い直す運動」であり、ひいては「カリフ制にせよ、他の形態を取るにせよ、国民国家を超えてウンマ全体を代表するインターナショナルな制度の確立を構想する主体として、イスラーム復興運動が登場している」という。マイノリティや女性の地位、経済格差についての指摘も。
国民国家とカリフ制―ラシード・リダーの「予言」(長沢 栄治 8/5)
…多くの矛盾を抱えながらも、国民国家の成熟のプロセスは、中東およびアラブ世界において、紆余曲折を伴いつつ現在も進行している、と筆者は考えている。その場合、3年前に始まったアラブ革命は、こうしたプロセスの大きな画期となるであろう。今回のアラブ革命とは、60年前のアラブ革命の時代に国民国家として大きく成長したアラブ諸国の体制に対して、その国民統合のあり方を改めて問い直す運動として起きていると考えられるからである。
今回のアラブ革命は様々な問題を提起したが、その中で注意すべきは、マイノリティ問題であろう。たとえば、革命の波に対応して、モロッコは立憲王制の改革という開明的対応を示したが、その一環としてアマジク語(ベルベル語)を公用語として認めたことは注目に値する。エジプトの場合でいえば、ヌビア人が失われた故郷に対する権利を主張し始めたし、宗派対立で死者は出たが、シーア派の存在も確認された。武装過激派との関係で問題になったシナイ半島のベドウィン系住民と中央政府との関係も、革命が揺り動かした国民統合の問題として扱うことができる。
また、もちろんマイノリティではないが、アラビア語で言うところの「世界の半分」の女性の地位をめぐる問題は、実は国民統合の重要な側面であった。そして、経済開発と所得分配の問題もまた階級間の「亀裂」を修復するという意味で国民統合の重要なテーマである。とくに現在において、ネオ・リベラリズムのグローバルな経済潮流が生みだしている極端な階級格差に対して、市場に介入する国民国家の役割が期待されている。
また、国民統合をめぐる重要な問題として、国民国家と地域システムとの関係についても言及する必要がある。地域システムとは、上で述べたアラブ国家システムなど、一群の領域国家が作る国家システムのことを指す。すでに述べたように、中東には、周りに迷惑をかける自分勝手な国民統合の顕著な事例があるが、その一方で、各国で進行する国民統合のプロセスに対する外部からの露骨な介入も見られる。今回のアラブ革命においても、各国で行なわれる変革の動きに対して、国外からの干渉や介入がなされた。
周辺国からの介入外交の結果、イエメンでは中途半端な形で政権交代がなされただけで問題は先送りされた。バハレーンでは外国の治安部隊の介入によって運動が弾圧された。さらには、外部からの軍事的介入がなされたリビアとシリアでは、国民統合の進展どころか、国家解体の危機に陥っている。既存の国家における国民統合のあり方をめぐる対立や変動は、諸国家間の関係、そして域外からの介入の動きと密接に結びついて展開する。このような複雑な相互干渉の関係を通じて現実のアラブ国家システムは機能している。国民統合をめぐる基本的な問題が国境を越えて展開していると言うことができる。
■ イスラーム復興運動の試練
ここでカリフ制の復活をめぐる議論に話を戻したい。1920年代と現在との間の大きな相違は、アラブ・イスラーム諸国の国民国家としての成熟である。この共和国を標準的な形態とする国民国家の体制の下では、かつて議論されたオスマン帝国のカリフの継承といった王制を前提とするカリフ制の復活はもはや考えられない。そして、もう一つの重要な相違は、イスラーム復興運動の成長である。すなわち、カリフ制にせよ、他の形態を取るにせよ、国民国家を超えてウンマ全体を代表するインターナショナルな制度の確立を構想する主体として、イスラーム復興運動が登場していることである。
イスラーム復興運動は、社会と国家体制の「再イスラーム化」を目指す運動として出発し、それぞれの国民国家の枠内で成長してきた。そしてさらに高次元の目標として、国民国家を越えたウンマの連帯の新しい形を作りあげることを夢に描いている。それは「ウンマの理念と実践に立脚するシステム」(小杉泰『現代イスラーム世界論』)を制度化し、さらに現実の国民国家を構成要素とする世界システムと接合し、さらにはそれを包摂しようとする構想である。新カリフ制は、そのオプションの一つであり、最もラディカルな提案である。つまり、カリフ制の樹立を通じて、既存の国民国家をすべて否定し、イスラーム世界の政治的統一を達成しようというのである。
もちろんイスラーム復興運動は、一様ではなく、それらと国民国家との関係も一括りにすることはできない。その場合、一つの参照事例となるのが、昨年の軍事クーデターによるエジプト・ムスリム同胞団政権の崩壊である。ここでもクーデターに対するサウジアラビアやUAEの支持と新政権に対する財政支援という「介入」がなされた点も確認しておきたい。今回のムスリム同胞団が直面している試練は、イスラーム復興運動と国民国家との関係を考える上で重要な意味を持っている。ムスリム同胞団は、国民国家のイスラーム化に加えて、さらにその向こうにどのようなビジョンを持っていたのだろうか。政権からの転落後、ムスリム同胞団は、国家・民族の裏切り者であり、アル=カーイダと同類の国際的な陰謀とテロのネットワークの一部だ、との非難キャンペーンを浴びて徹底的な弾圧を受けている。しかし、いわゆる「中道派」として評価されてきた彼らが、ウンマの理念と実践に立脚する国際的な制度として何を構想していたのか。それは国内の「再イスラーム化」改革構想とともに、今後の運動再生に当たり、見直すべき検討課題となるであろう。
付記 10/6
最近イスラム法やカリフ制について目についた論考いくつか。
・「アッラーを立法者とする法(シャリーア)」からヨーロッパ近代法への問い――ジハードをめぐって | SYNODOS -シノドス (奥田敦 4/8)
・イスラーム国の論理とそれを欧米が容認できない理由 (VIDEO NEWS.com 10/4)
・CISMOR講演会「東西間のイスラーム・カリフ制 −歴史的考察と現在の展望」(2011.3.12 同志社大 中田考氏、内藤正典氏のコメント動画は必見)
11/13
中田孝氏が、カリフ制とイスラム国について、朝日中東マガジンに連載を始めた。
・イスラーム国とカリフ制(1) カリフ制の歴史的成立 (11/11)
2015.2.21
朝日中東マガジンは編集長の川上さんが退職したため廃刊となってしまった。上記の記事を含め、貴重な記事が山ほどあった。アーカイブとして図書館では読めるようだけれど、個人がインターネットでどう読めるのかがよくわからない。これまでのようにデジタル版購入読者が気軽に読めるようにしてほしいんだけれど…。
2/17日には、中田孝氏の『イスラーム 生と死と聖戦』が出た。中田氏によるイスラム法とカリフ制についての解釈と構想が、研究者やムスリム以外の一般読者を対象に、噛み砕いて書かれている。
イスラムについては、イスラムの側から非イスラムに向けて書かれたものが少ないのではないかと思っていた。イスラムに対する誤解や先入観を払しょくするためにも、私たちがイスラムと共存していくためにも、イスラム研究ではなく、イスラム勧誘でもない、わかりやすい解説が必要ではないかと。中田先生のこの本は、その意味で待ち望んでいた本だ。
イスラムはムハンマドに下された神の啓示を、唯一絶対で、かつ最終的なものだとしている。この「神の法」は無謬であり、人間が勝手に変えたりすることは出来ない。このことからイスラムは非常に硬直した宗教だと思われがちだが、この本を読むと、実は柔軟な解釈によって長い時代を生き延びてきたということが良くわかる。
中田先生のカリフ制は、「イスラム国」の暴力を批判する。ただし批判は、「イスラム国」を生んだ「領域国民国家」の暴力性に対しては更に、否定的に、厳しい。「イスラムはアナーキーなイデオロギー」という氏の「カリフ制」は、「領域国民国家」で成り立っている世界の現実にとって、「イスラム国」よりもっと危険なものであるかもしれない。危険であるというのは、その構想がイスラムという限定的な共同体の樹立を目指すだけでなく、平和なユートピアを目指すものである以上に、この世に「公正」を求めるものだからだ。
イスラームの壮大な世界観や生活規範を知る本であり、ISILについて知る本ではない。拙速な読まれ方がされないよう願いつつ、やはり多くの人に読んでもらいたい。 イスラーム 生と死と聖戦 (集英社新書) http://t.co/F5pMzE9G7i@amazonJP
— 香山リカ (@rkayama) 2015, 2月 19
2/20日に出たこちらはまだ読んでいいなけれど。
『週刊読書人』のインタビューも、
これは読まなくちゃと思わせる内容。





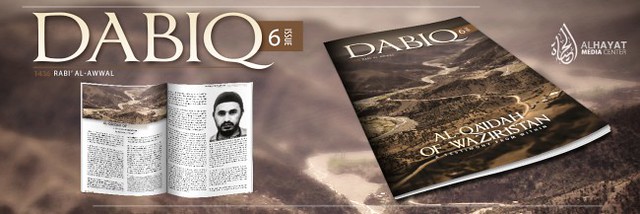





コメント