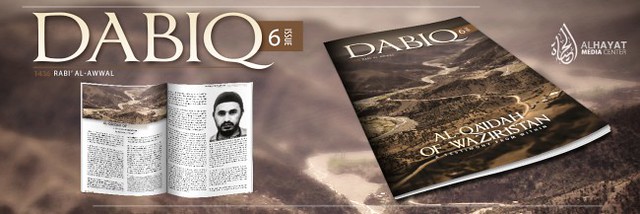
ISの機関誌ダービク 開かれたページの写真はISの創設者ザルカーウィ
「イスラム国(IS)」には外国人戦闘員が1.5~2万人ほど参加しているという。
戦闘で死んでしまったり、
帰国したりする人たちもいるだろうに、人数にそれほど変動がない。
絶えず流入し続けている、ということだろうか。
出身国は80か国とも90か国とも言われている。
いったいどのような人が ? との疑問に、日本では、
20年前のオウム真理教を重ねる声を聞く。
さすがに研究者の論評には見ないけれど、
パラパラと、ISそのものを「オウムみたい」と口にする人もいる。
まず、北大生のシリア渡航計画(の頓挫)の発覚で、「カルト的な宗教に高学歴で優秀な若者が惹かれる」のがオウムのようだ、という類推がある。それまで、それらしい兆候も見せずにいた若者が、ある日突然家族のもとからいなくなる。周囲は彼らの動機が理解できず、「洗脳」されたのだという結論に至る。20年前の地下鉄サリン事件は中高年世代にはまだ鮮明な記憶で、にもかかわらず、オウムの何が若者たちをそれほど惹きつけたのかは今もって理解できずにいたりするので、こんな類推も出てくるのだろう。
ISという組織やその活動をオウムに重ねる見方は、なんだかわけのわからない宗教団体が大量殺戮を行い、尋常ならざる教義でそれを正当化している、その上ISは、これからは日本人も殺害対象だと脅している、オウムのサリン攻撃のように無差別だし、怖い、不気味だ、といったところか。
幸いなことに日本では、この20年、オウムを除いて「テロ」とされるような事件は起きていない。なので比べる例がオウムしかない、ということはあろう。けれども私は、「でも、違うよね、それ」と思っていた。ぼんやりと思っていただけだったが、このあたりで整理しておこうという気になった。ISをめぐる状況は目まぐるしく変化している。4月にはイラク側のISの「首都」モスルの奪還を、有志連合が敢行するとのニュースもある。その前哨戦ともなる戦いが、ティクリートをめぐって、イランの革命防衛隊の支援を得て始まった。それだけに、である。
イラク軍、IS(イスラム国)へ過去最大の軍事作戦を開始/Hurriyet紙 (SYNODOSが選ぶ「日本語で読む世界のメディア」3/6)
IS戦闘員とオウム信者
ISに戦闘員が一番多いのは、イラク・シリア以外ではイスラム圏の国である。正確な数字はわからないが、チュニジア(1500~3000人)、サウジアラビア(1500~2500人)、ヨルダン、モロッコ(ともに1500人)と、中東・北アフリカだけで過半数を占めるという。
イスラム国の外国人戦闘員2万人超(日経 2/6)
この人たちはムスリム(イスラム教徒)であるので、カリフ制による理想のイスラム国家樹立や、第一次世界大戦からイラク戦争に至る、暴力的な欧米の中東政策に対する反発で共感していると考えられる。それぞれの国の問題で充分「過激化」していたかもしれないし、アフガニスタンやシリア内線などですでに義勇兵として戦った経験のある人たち、あるいはそれらの人たちに感化された若者もいるかもしれない。ということは、彼らにとってのIS支配地域は、イスラム圏に通底する先鋭な問題の戦闘の場なのだ。
これらの戦闘員より欧米にとって重要なのは、自国民の参加者である。帰国後のホームグロウンテロを恐れるのである。その数最大4000人(うちフランスが1200人。人数は全て上記記事より)。多くはイスラム圏からの移民二世・三世とされる。彼らは欧州各国において、その国の国民として生まれ育っているが、どの国にも、同化政策か多文化主義かを問わず、移民たちにとってのダブルスタンダードが存在し、教育や就業といった生活全般で疎外感や実際的な差別や格差を味わい、帰属意識やアイデンティティーの確立にも苦しんでいるという。彼らがイスラムへの「再覚醒」を経て先鋭化し、居場所や使命感、理想社会を求めてISに参加するのである(これは、中東・イスラム圏の問題ではなく、まずは欧米各国の国内問題として考える必要がある)。
また、欧米のアラブ・イスラム系でない人たちがいる。根っからの欧米人で、イスラムに改宗した後にISに入ったのか、ISに入るために改宗したのかはわからないが、新たにムスリムとなった人たちだ。彼らの動機が理解できず、「洗脳された」と家族や周囲が捉える人たち。もしオウムに対比して考えることが可能だとして、対象となるのはこの人たちだろう。では、彼らの動機はオウムに入信した動機と同じだろうか。受けたとされる「洗脳」はオウムの「洗脳」と同じだろうか。
バブルが全盛から崩壊に向かう日本で、オウムへの入り口は神秘体験や精神世界への興味だった。オウムの暴力は、教団内部の暴走という側面と、「最終戦争」や「世界征服」の手段という二つの側面を持つが、実際の殺人に至る暴力は、対外的だけではなく一般信徒にも隠されていた。
一方ISのプロパガンダでは、「殉教」や殺戮は美化され、実際より大袈裟に宣伝されている。数で言えばシリアのアサド政権の空爆による民間人の死者の方がはるかに多いし(20万人超)、拷問や不当な「処刑」は、アサド政権やイラクの前マリキ政権も行っていた。異なるのは斬首などの衝撃的な映像がプロパガンダとして利用されている点である。これらの情報は、誰もがネット上で閲覧できる。つまり彼らは、「洗脳」されたか否かは別として、ISが行っていることがどういうことかを、あらかじめ知っていたのだ。ヨガ教室に参加したつもりでいたのがいつのまにか自爆ベルトを巻いていた、は、IS参加者にはいない、ということだ。そしてもう一つ、いったいこのような人たちは何人くらいいるのか、である。オウムの信者は一時1万人いたというが、そのような有意な数字なのかどうか。
この他には、旧ソ連領からの参加者が3000人いる。上記記事の数字には出てきていないが、中国から参加するイスラム教徒もいる。日本では取り上げられることの少ない人たちであるが、数としては多い。
常岡浩介氏は『イスラム国とは何か』で、三回にわたって潜入したIS支配地域で、接触した戦闘員の生の声を紹介している。常岡さんが話を聞いたのは、トルコから密入国する際に道づれになった人や、宿舎などで出会った人たちということもあって、外国人戦闘員がほとんどである。出身国は29か国。やはり多くはイスラム的な大義やカリフ制の理想に惹かれていたという。このインタビュー形式の本は、IS内部を直接見聞きした報告と分析であるが、なかでもチェチェンからの義勇兵の話は、初めて耳にする、貴重なものであった。
常岡さんは元々チェチェン戦争をゲリラ側で従軍取材していた。IS支配地域に入れたのも、その彼らとのネットワークがあってのことだ。彼らはロシアからの独立闘争を戦った後に難民化した人たちで、司令官一下部隊ごとISに参加していたりする。目的は、ロシアが支持するアサド政権を倒し、最終的には故郷を解放することだという。また、中国のウイグル族やカザフスタンから来た人たちは、自国でのイスラム教徒への弾圧から逃れてきていた。彼らは「生きるために」故郷を捨て、ISにたどり着いた人たちだ。
いずれにしても、彼らの行動を支える理念として、ISの主張する、周辺イスラム独裁国の暴政(及び欧米の地域介入の暴力性)に対するカリフ制再興はある。それが「(欧米)世界秩序」への挑戦と考えられる点も、大きいかもしれない。かつての事例に重ねるならば、これはオウムではなく、「世界同時革命」を唱え、パレスチナPFLPへの連帯を表明し、テロへと突っ走った日本赤軍であろう。
これらの人たちに共通する、宗教以外のものもある。参加者にはイスラム的な正義などどうでもよくて、ただ人を殺してみたい人や犯罪者などもいると言われている。そのような人まで含めて共通するのは、それが手段であれ、目的であれ、求めているのが戦闘そのものだということだ。
日本からの参加者は、判明しているのは、実は行かなかった北大生だけである(もともと行く気などなかったと、常岡さんは見ている)。シリアの内戦まで広げても、知る限りでは、自由シリア軍に参加してISに殺害された湯川さんと、反アサド武装組織に参加し、負傷して帰国した元自衛官がいるだけである。彼らの動機も、精神世界への興味でも神秘体験でも自己救済でもなく、戦闘すること、戦闘の場に身を置いてみること、であった。今後日本からの参加者が出てくるかどうかはわからないけれど、少なくとも宗教性を求めてのことではないだろうと、私は思っている。
背景としての貧困はどうだろうか。欧米の移民二世・三世に構造的な経済的格差が問題であるのは確かだし、参加者の多いイスラム圏にも同様の問題はある。欧米では貧困そのものより、貧困状態を強いられることに対する怒り、あるいは絶望のほうが強いかもしれない。ただし、富裕層出身とされるジハーディ・ジョンのような人もいる。あくまで個々の背景の一つと言うべきだろう。
このように、ISに参加する外国人には、それぞれの動機や目的にばらつきがあるものの、彼らをISへと押し出す誘因として、出身国の政治社会問題があるという点がもうひとつの共通点だろう。また、アフガニスタンだけでなく、チェチェン戦争でも、ゲリラ側に他のイスラム圏から多数の義勇兵が集結した。イスラムの戦いに国境を超えて参戦する行為は、イスラムに根差した「伝統」でもある。
参考までに、戦闘員で数が一番多い地元住民に関して、興味深い記事があったので紹介しておこう。
「毎月200 ドルの固定給がもらえ、武器や車も与えられると聞いてISに入った。家族も当初は喜んでいた」。ISの元検問所担当、アブファハド氏(25)はこう話す。 ISの「首都」ラッカの農家の四男。家族12人全員で働いても月収は250ドル程度だった。2013年春、ISに入り、毎日6時間おきに計12時間働い た。「激務だったが、同じ額の収入を毎月得られる仕事は他になかった」
ISに希望も感じていた。「イスラム国家の建設という言葉に興奮し た。13年春ごろからラッカの町中にISの旗やポスターが掲げられ、治安も急激に良くなった」。数百ドルの現金と引き換えに、15歳前後の息子をISに預ける親もいた。逆に子供が勝手にISに加わるケースも相次ぎ、「心配した親が家族でトルコに避難した例も多数あった」。
13年6月から 14年夏にかけてISに所属していたアブウサマ氏(26)によると、地元住民がISに加わる主な動機は(1)政治的判断(2)金(3)信仰だ。(1)はアサド政権の元支持者にも多い。戦闘が長期化するなか、有利な側につきたいとの思いだ。 (2)は生活困窮者に多い。特にラッカの主産業である農業は戦闘の長期化で農地が荒廃。収入源を失った市民が少なくない。(3)は「イスラム国家」の建設 という目標で主に若者らを引きつけているという。
緩やかなネットワークが特徴の「アルカイダ」と異なり、ISは「首都」を構え、イスラム国家という「目に見える」目標を掲げることで、長期の戦闘に疲弊した地元住民や、日常に希望を見いだせない外国人らの心を捉えている。
注目すべきは、目的の一番目が政治的判断であるという点だろう。取材に応じたのはISから抜け、トルコに逃げてきた人たちだ。彼らは「イスラム国家の建設という「理想」や高額の報酬に期待したものの、やがて「現実とのギャップ」に失望したと口をそろえた」という。
IS:元戦闘員 理想と現実とのギャップに失望(毎日新聞 3/3)
こうして見てくると、オウム入信のわけのわからなさに比べて、IS参加の動機のなんという明解さか、と思う。そこには、戦闘と、戦闘の果ての解放(「殉教」による即時天国行きも含まれるかもしれない)が、具体的、現実的に目に見えるものとして、想起されているのだ。アサド政権からの、シーア派政権からの、サイクス・ピコ協定からの、欧米のイスラム敵視・攻撃からの解放としての「カリフ制国家」。これは私たちの目から見たら、宗教行為というよりも政治活動である。ただイスラム教徒にとってのみ、信仰の実践とカウントされるのだと、私は理解している。
上記記事では、地元戦闘員がISから逃げてきたことにも注目するべきだろう。取材に応じた人は、冷静に損得を考えてISから抜けてきたわけだ。常岡さんも書いているけれど、外国人戦闘員も頻繁に所属を変えるという。地元住民にとっては国境まで越えなければいけないほどのリスクがあるにしても、「現実とのギャップ」を感じれば離反するし、より得るものが多かったり、理念行動に共感を失えば別組織に移る、ということだ。ISがそのような逃亡・離反者を「処刑」したというニュースはある。暴力による恐怖支配は内部でも行われているだろう。けれどももし戦闘員が「洗脳」されているのなら、離脱を恐怖支配で食い止める必要はない。プロパガンダに惑わされて参加したとしても、それは「洗脳された」のではなく、「だまされた」のである。これもまた、オウムとの大きな違いだろう。
ISとオウムの宗教的、あるいは宗教を超えた比較
ISにオウムを重ねる人たちは、きっと、宗教による殺人の正当化という点にフォーカスしているのだと思う。けれども、ISを見るときも、他の中東・イスラム圏の問題を見るときも、あるいはイスラムそのものを見るときも、私たちが陥ってはならない一番大きな陥穽が、イスラムが宗教のみをさすと考えてしまうことだと思う。この点を頭の隅に置いて、ISとオウムを、いくつかの側面から比較してみよう。
(参考記事:イスラムは何故政教分離が難しいのか — 国家と宗教)
①イスラム原理主義とカルト宗教
ISは「イスラムテロ組織」とか、「イスラム過激派」、あるいは「イスラム原理主義組織」と形容される。オウムは「カルト宗教団体」であろうか。いずれも反体制的かつ暴力是認で一見共通しているように見える。だが、前提となる部分に大きな違いがある。それはイスラムの存在である。
「イスラム原理主義」というのは英語の Islamic Fundamentalism の訳によるもので、もともと英語にもなかったのが、アメリカの Christian fundamentalism から転用された言葉だ。「キリスト教原理主義」には、原理的な宗派に対する批判的かつ差別・侮蔑的な意味も込められているというから、「イスラム原理主義」にも同じニュアンスはあるだろう。イスラム圏にはもちろんこの言葉はない。
イスラム社会では、イスラムに原理的で先鋭的な理念をサラフィー主義と呼ぶ。厳格なイスラムの実践を通して自分たちの理想の共同体を志向するもので、それを武力によって行うのがジハード主義である(ジハードには宗教的な努力奮闘など別の意味もある)。ゆえにISは、サラフィー・ジハード集団と形容される。これが私たちが「イスラム原理主義」と呼ぶものに一番近い。
近いどころか同じじゃないか、と思われるかもしれないが、サラフィー主義は、「キリスト教原理主義」のように単なる(政治的力の大きい)一宗派などではない。13世紀に遡るイスラム復古思想で、本来は平和的なものだ。社会改革のときに勢いが増してイスラム復興運動となったりする、現在につづく大きなうねりの基となる理念である。ばかりではなく、サウジアラビアはサラフィー主義の国として建国された。このような点からも単なる「原理主義」とはまったく意味合いが異なる。イスラムの「宗教改革」の一つの潮流であり、今もって大きな勢力でもあるのだ。宗派的にはスンナ派の思想・運動で、エジプトで生まれたムスリム同胞団などのように、貧富の差による困窮者救済のボランティアに力を入れる福祉・社会活動もこのサラフィー主義であるし、利子を禁じた「イスラム金融」もサラフィー主義によっている。
ということはサラフィー主義は、「キリスト教原理主義」やオウムなどの新興宗教とは全く違う、肯定的かつ親和的な意味合いとポジションを、イスラム社会の中で得ているということである。それどころか、腐敗が進み、イスラム的な公正が顧みられない社会で、かつ抑圧的な独裁国家の国民には、サラフィー主義の理想主義や反政府的な主張に、むしろ共感や理解が広がっているとも言える。また、このサラフィー主義のなかには、イスラムの理想的な共同体を100年ほど不在のカリフという宗教・政治指導者を復活させて実現させようという動きもある。
つまり、私たちが「イスラム過激派/原理主義」と呼んでいるものは、まず基盤にイスラムという世界普遍宗教・政治イデオロギーがゆるぎなく広がり、二階には原点回帰改革派のサラフィー主義が安定的に乗り、その一部がカリフ制再興によるイスラム理想社会を志向し、その上の三階にようやく、理想社会を暴力もいとわずに実現させようというジハード主義が乗っている、という三層構造の、一番上の部分なのだ。
オウムはといえば、宗教法人としては解体しているし、信徒は別の宗教名で残ってはいるが(1800人程度とのこと)、まともな宗教としての社会的認知はないと言えるだろう。「カルト」と規定されれば教義すらまともに取り上げられないオウムと、一階と二階部分までが広く社会的認知を得ているサラフィー・シハード集団とは、まったく違うものなのだ(この点で、ISは日本赤軍とも大きく異なる)。
②それぞれの社会的背景
オウムとISでは、誕生の経緯と背景が大きく違う。そんなの分かりきったことじゃないか、と思われるかもしれないが、オウムを対比させること自体が、この違いを無視、とまでは言わなくても、軽視していることの証のように、私には思える。
モノにかこまれ、水と安全がただで手に入る日本は、第二次世界大戦で自分たちが行ったことさえ風化している、平和で「平等」な(一応は)民主国家である。
比して中東は、100年前の第一次世界大戦から続くの負の遺産を、ずっと引きずってきた地域だ。英仏露の密約による国境線に従って分割された植民地は、第二次世界大戦後、その国境線のまま独立した。ある国は王国に、別の国は共和国となった。だがこれらの国々は、部族社会の上に乗った独裁体制という点で共通しており、いずれの国民も、程度の差はあれずっと暴政に耐えてきたのだ。
この地域的な問題に関して、欧米は端を発しただけでなく、その後の独裁体制を石油利権に有利な限り支持し続けただけでもなく、パレスチナの土地をこれまた密約によりイスラエルに与え、その後のパレスチナへの「入植」 とガザ攻撃にも見て見ぬふりを決め込み、自らに都合のよい「国(=民主国家)造り」や「テロの撲滅」を口実に、でっちあげの理由による戦争まで仕掛けて、「積極的」に介入してきた。
ISを生んだ直近の原因が、2003年のアメリカ(と有志連合)によるイラク戦争とその占領政策の失敗、つまり宗派対立の激化にあることでは、内外の見方は一致している。すぐ隣のシリアでは、「アラブの春」が内戦となり、周辺イスラム国家、及び欧米、及びイラン・ロシアからの武器の流入による代理戦争と化して、戦乱はいつ終息するとも知れない。ISの伸長は、「アラブの春」が暗転したひとつの帰結だということが出来る。
ISでクローズアップされるのは何よりも暴力的な手法であるが、それを脇に置いて見れば、彼らの主張のなかには、地域社会の人々の長い間抱えてきた怨念や、「不公正」からの脱却の権利や、理想社会をめざず希望のようなものすら、読み取ることが出来る。ISの真の動機や目的が100%これらの思いに重なるのかどうか疑問はあるけれど、ISに参集する人々に占める心情に、この部分への共感があることは間違いない。それを支えるのがイスラムの「大義」である。ここに政治的な動機と宗教が混淆してある。
これは、精神世界や神秘体験を入り口に、やがてカルト的暴走を辿るオウムとは全く異なる。彼らの内的誘因に社会背景も無縁ではないだろうけれど、ISが誕生した地域に厳然と存在する、生存すら脅かされかねないような深刻な問題はない。ISの誕生は、中東イスラム社会の必然だと言うこともできる。日本にオウムを生む必然があったとしても、それは全く違うものであろう。
③カリフと尊師
オウムは、地下鉄サリン事件後に尊師麻原彰晃をはじめ幹部が逮捕され、解体した。後継団体が二つあり、少しずつだが信者も増えているというが、カリスマ的なリーダー無き後、しかも犯した犯罪や、LSDや電気ショックなどの「修行」の「邪道」性が明らかになったうえでは、かつてのような規模を取り戻すのは難しいだろう。
カリフ制については、以前、あれこれ考えたり疑問に思ったりしたことを書いた(あらためて、カリフ制って何 ? )。ISの指導者バグダーディーがそのカリフを宣言したわけだけれど、これには「自称」というのを頭につけるべきだろう。16億の人々がバイア(忠誠)を誓うのはあまりにあり得ないからだ。だが、それなりの風格やカリスマ性はありそうだ。では、彼がビン・ラディンのように、あるいは旧イラクのフセインのように殺害されたとしたらどうだろう。尊師なき後のオウムのように、解体するだろうか。
まず、オウムはあくまで日本の一宗教団体にすぎなかった(海外にいくら支部があろうとも)。どれほど疑似国家たろうとしても、地元住民を取り込むどころか反対運動まで引き起こし、支持や統治を組織内部以上に広げることは出来なかった。サリンによる攻撃は多くの死者や被害者を出し、結果的に彼らの壊滅的な敗北を招くことにもなった。彼らは国家内部で犯罪行為を行い、逮捕され、裁かれているに過ぎない。
IS に関しては、彼らはすでに国家である(と私は思う)。領土と国民を擁し、法と制度を有し(ISには既にしてイスラムがあるのが大きい)、統治するのが国家だとしたら、ISはこの条件を満たしている。わざわざISILと呼べ、と言わなければいけないことからして、既に事実として国家であることを語っている。周辺国や国際社会がそう認めたくない、認めない、という一点だけで「国家」でないだけである。アサド政権のほうが、ISよりよほど国家ではないのではないか、とも私は思っている。ISは、シーア派や異教徒や自分たちの統治に従わない人や人質を「処刑」しているが、自国民に無差別にたる爆弾を落としたりはしていない。
もちろん、安定した国家には程遠く、有志連合がついに地上戦に打って出れば、イラク戦争のように米軍の大軍が侵攻すれば(考えたくないが、そうなれば自衛隊派遣が要請される可能性もある)、ISという国家は物理的には消滅するだろう。けれども、解体してばらばらになったISの理念は飛び散り、飛び散った先で増殖するだろう。その時カリフはまたいなくなるかもしれない。だがカリフなどいなくても、増殖に問題はない。私が一番恐れるのはこの事だ。崩壊後の無秩序と暴力の拡散が一体どのように収拾可能なのか。
実は、この「飛び散って増殖」は既に始まっている。アルジェリアで、リビアで、エジプトで、ナイジェリアで、パキスタンで、インドネシアで、フィリピンで、ISの傘下に入ると宣言する武装集団が登場している。今まであった組織がハクをつけるために名乗りを上げていたりもするけれど、「カリフ国」というのは別に地理的にISを核に領土を広げていかなくともいいのである。ただカリフに忠誠を誓えば、そこはカリフの国となるのだ。この点からも、それぞれの国にとっての最優先課題は、有志連合で空爆や地上戦に参加したりすることよりも、国内問題の解決である。IS攻撃は自国内の組織の暴力の口実にしかならない。
ここで思うのは、ISに参加を希望する人たちへの渡航制限である。有志連合が国籍はく奪を法制化したり、渡航阻止に力を入れているけれど、これは自国内の「テロ撲滅」に本当に有効なのだろうか。彼らがISの掲げる理想やカリフ国に「現実とのギャップ」を感じて帰国したら、彼らは自国でISの指示に従ってテロを起こしたりしないだろう。むしろ渡航を阻止された方が、ISへの忠誠心、というよりも、その国への反抗心や憎悪、絶望感は高まるのではないか。
振り返って、尊師(とそのとりまき?)が作り上げた、ファナティックで怪物的な世界観や強迫観念は、この20年間を見ても、1万人の信徒によって拡散されなかった。それ以前に、大前提として、イスラムには人間を神や絶対的な存在とする個人崇拝はあり得ないんだけれど。
④ISはポルポトなのか
ポルポトは、批判を恐れて知識人を虐殺した。それが暴走して、批判精神や知識の無い子供を重用し、その子供たちが大人を殺害するようなことにまでなってしまった。ISの極端な宗教解釈は、教育から音楽や歴史や科学を排し、宗教にのみ限定しているという。この点でもポルポトを想起させるけれど、一点において大きく異なっている。やはりそこにイスラムがある、ということだ。
バグダーディーは、2014年6月のカリフ就任後の集団礼拝の説教で、私がアラーとその使徒に従う限り私に従え、私が背いたなら私に従う義務はない、私がイスラムとして誤った行いをした場合はそれを正してくれ、と演説している。これはムハンマドの後継者となった初代カリフ、アブー・バクルが述べた言葉にならったものだ。ちなみにバグダーディーは、アブー・バクル・バグダーディーと、名前まで初代カリフからとっている(本名ではない)。
イスラムに決定的なのは、神の法が全ての上に来ることである。近代国家は戦争や暴力の行使権を国家にのみ独占的に与えているが、イスラムの考え方では本来的にはこれはない。また、イスラムでは信仰は神と個人の一対一のものとされている。国家や指導者が誤ったとき(不完全な人間は常に誤るものとされる)、それを糺す権利が全ムスリムにはあるのである。つまり造反有理なのだ。ゆえにジハード主義も出てくるわけだけれど、そのときの根拠は、あくまでクルアーンとムハンマドの言行録によるイスラムの教えなのだ。
ヤジーディ教の女性奴隷化も、彼らはクルアーンを引き合いに出して弁明しなければならなかった(奴隷という言葉に過剰に反応しがちだけれど、これは戦場における性犯罪として考えなければいけないと思う)。これまでにない方策を取ろうとした時、そこには常にクルアーン上の正しさが求められる。カリフ制再興を掲げ、イスラムとしての純粋性を、たとえ建前だけでも打ち出している以上、ポルポトのように非生産的な方向が支持されるとは思いにくい。イスラムとは非常に現実的な宗教でもある。一個人であっても、イスラム的に正しくもなく、かつ非現実的であると判断すれば、信仰が強ければ強いほど、原理的であればあるほど、彼はそれに従わないだろう。
このことから、ISがイスラム的にどんどん道を踏み外していけば、彼らへの支持は減り、崩壊が加速していく可能性も考えられる。とすればここに、ISの暴力性を削ぐためのひとつのアプローチもあるわけだけれど、それはあまりに時間のかかる遠回りな取り組みで、恐ろしいのは、崩壊に対抗しようとしての暴力の暴走がそれらをスピードと質量において凌駕してしまうことだ。ポルポトの知識人への断罪のように、エスカレートしていく内部的な暴力の局面で、それに歯止めをかける力がどこまで彼らのイスラムにあるのか。あるいは外部から、どのような形で歯止めとなる平和のイスラムを発信し、伝えていくことができるのか。
もしかしたら局面は変わりつつあるのではないかと思えることの一つに、古代遺跡の破壊(の宣伝)がある。ISには常に、自分たちの突出性や優位性を誇示する必要がある。外的にはこれからのIS参集者に対して、そして内的には参集者に留まってもらうために。そのための行為はセンセーショナルで、かつビジュアル的な迫力もなければいけない。遺跡破壊にはイスラムの偶像信仰の否定という大義名分もあるし、「処刑」による恐怖支配より彼らにとっての費用対効果は高い。ただし、めぼしいものは売り払ったうえで(どうせなら売り払って欲しいと切に願う)。
(※付記:遺跡破壊のニュースが続いている。胸潰れる思い。この件は別記事に書いているので、そちらに追記して行くつもりである)
⑤暴力はどこから来て、どこへ行くのか
イスラムを宗教とだけ見るべきではないと、先に書いた。シリアの地元民もIS参加の動機を、まずは政治的なものであり、次が経済的なものであり、最後に宗教だと述べていた。ISは宗教としてのイスラムを強烈に前面に出して訴えているし、また、外国人戦闘員には宗教的な動機が強いにしても、ISの行っている行為が宗教にのみよるのかということは、考えてみるべきであろう。
ISがこれほど短期間に領土を掌握できたのは、旧フセイン政権の生き残りであるバース党の幹部や軍部、官僚組織がISに参加しているからだという。彼らは徹底的な世俗派である。また、あれだけ少ない構成員で統治が可能なのは、シーア派の旧マリキ政権で差別・粛清を受けたスンナ派部族が、部族長の政治的判断によりIS支持にまわっているからだ、とも聞く。
これまで、サラフィー・ジハード主義カリフ制再興組織と世俗領土利権獲得政治集団は、決して混じり合うことがなかった。バース党を率いたフセインは、アルカイダを嫌いぬいていたという。そのフセイン政権の残党と、一時はアルカイダの傘下にもいたジハード集団の連合体がISだとすると、これは今までにないハイブリッドな組織だということが出来る。
ISの最大の目的は「国家たらんとすること」だと、常岡さんは言う。イスラムの理想であるカリフ制国家の樹立、という大義名分の陰には、バース党が失った領土再獲得への執着があると、『イスラム国 テロリストが国家をつくる時』(ロレッタ・ナポリオーニ/著)も指摘している。ナポリオーニはこれを「ISはアラブ・イスラムにとってのイスラエルを目指しているのではないか」とも分析している。全ユダヤ人にとっての神に約束された土地と、ムスリムであれば誰でも移住の義務と権利のある理想の共同体 — 確かに、構図は同じだ。暴力的に、力によって領土を獲得・拡張しようとする手法も、その政治性を「神」の名のもとに行う戦略も。
ISの暴力性は、イスラム法の厳格で酷薄な解釈によるものだとされるが、常岡さんは、バース党の残虐性や暴力による恐怖支配を踏襲している、やり方がそっくりだ、という。世俗的な組織とイスラム主義組織は、暴力の利用価値においても一致したのだろうか。けれどもあの地域の政体は、ずっと暴力による支配で統治をおこなってきたのだ。シリア政権がスンニ派の反政府組織弾圧で、ハマという町の住民全員2万人(4万人とも言われる)を虐殺したのは、現アサド大統領の父親ハーフィズ・アサドであった。1982年のことだから、そう昔のことではない。イスラエルは恒常的にガザを爆撃する。監視と密告と拷問、処刑、土地の強奪と分離壁、そして懲罰としての空爆。中東イスラム圏一帯は、これらの暴力が常態化した社会だった。
絶望にかられる。今、「中東イスラム圏一帯は、これらの暴力が常態化した社会だった」と過去形で書いたけれど、暴力はまぎれもない現在形であり、進行形であるからだ。ISの暴力は、これまでの暴力の上に乗っている。ISの暴力のすぐ隣で、別の暴力がまかり通っている。ISをつぶすとしてより強大な暴力が、唯一の手段であるかのような顔をして集結している。ISの暴力は許しがたいことだけれど、最後にやってきた正義面した暴力の真の目的が、地域一体で長く暴力に苦しむ人たちを救うことでもなく、「監視と密告と拷問、処刑、土地の強奪と分離壁、そして懲罰としての空爆」を一切止める気もないということが、明らかだからだ。
一時アルカイダが衰退したのは、アメリカの「テロとの戦争」のためではなかった。「アラブの春」で、テロではなくデモによって独裁体制が倒れるのを、自由と解放と公正を求める人たちが目の当たりにしたからだ。ISの誕生を防ぐには、「アラブの春」の徹底的な支持しかなかった。自国の利権や理念のためではない、彼らの選択に対する無条件の支持。それはあまりに不可能なことではあった。それが出来ずに、彼らを助けるよりも、追いやるようなことしかできないで、ここまで来てしまった。この先、いったいどのような方策があり得るのだろう。
ISによる後藤さんと湯川さんの殺害に、私たちの心は痛んだ。おそらく、アメリカ人やイギリス人の「処刑」にはこれほど痛まなかったはずだ。異教徒やスパイとして「処刑」されたイラクやシリアの人たち、アサド政権のたる爆弾で死んだ人たちの死にはさらに。命の値段に軽重があるように、暴力に対する痛覚にも軽重がある。戦争が痛覚を感じない相手に向けて動き出すものだとすれば、暴力の最初の萌芽は、いつも私たちの心のなかにある。
今一つだけはっきりと言えるのは、日本のことだ。アメリカの戦争に加担して中東に自衛隊を派遣するようなことは、絶対にしてはいけない。戦争というのは、ただ破壊して殺戮して終わり、ではない。アフガニスタンでも、イラクでも、アメリカの戦後処理は成功していない。その結果は、ブーメランのように対戦国に返ってくる。対戦国だけではない。テロの増加と経済的損失が、どれだけ大きな痛手を世界に与えたことか。
誰もが指摘するのが、中東イスラムの人たちが非常に親日的だということだ(旅行で行っただけでもそれはわかる)。ということは、日本は中立的な立場で地域に介入できるということだ。この資産をもってすれば、日本にとっての安全保障を強化するだけではなく、地域の平和構築にも貢献できる。常岡さんも、宮田先生も、誰もかれもがこのことを指摘している。日本は平和的な非軍事支援を強化するべきだと、安倍さんすら言っている。ただし、非軍事支援をアメリカ追随の軍事支援のように口にし、次の言葉が自衛隊派遣であるのなら、どれだけ多額な非軍事支援を行ったとしても、私たちの信用も安全保障も、ひいては地域の安定も、失われていくばかりであろう。
※3月7日、14日加筆訂正
※オウムによる地下鉄サリン事件から20年となる3/20日、
複数の検証番組等を視聴した。
そのざっくりとした感想を別記事にした。










コメント