オウムについて考える時に、この人の視点をはずすわけにはいかない。地下鉄サリン事件後、教団に残る信者に密着したドキュメンタリー『A』『A2』を撮り、書籍化し、『A3』ではノンフィクションとして麻原彰晃の裁判を追った森達也である。その視点とは『A』撮影当初、「あなたたち現役の信者たちの現在を、とにかく既成の形容詞や過剰な演出を排除して、ドキュメンタリーとして捉えたい」というものだった。だがこの視点だけであれば、遠くから勝手な色を付けて描いていたものを近くに寄って見直す、というだけのことである。
いや、これだけでも、当時のマスコミ報道の狂熱バッシング一色からすれば、突出したものになっただろう。教団内部に入ってドキュメンタリーを撮ろうとしたメディアは、森を除いては一つもなかったからだ。常であればあたりまえのことを、つまり、外部からの隠し撮りや幹部インタビューばかりではなく、対象に密着した取材を他に先駆けて行おうとするマスコミ魂というか、職業的思考が、オウムに関しては機能していなかった。
マスコミ用に張られたロープをくぐって一歩教団の敷地内に入った森は、そこでカメラを、自分が今抜け出てきたマスコミの群れと、周囲の住民と、警察と、そしてその向うのものにも向けた。向けざるを得なかった。何故ならそれらの光景の密度が、あまりに濃かったからだ。こうして森は、「施設の中と外、その光景を当量に見る」という視点を獲得した。
タイトルにも、ある視点が込められている。Aとは、「タイトルなど何だって良いのだ」という意思表示だと森はいう。これは、タイトルに凝縮されるような言語化はこの作品に対しては無意味だとする、「無自覚な凝縮や象徴の危険性」に対する徹底的な拒絶宣言なのである。この姿勢は、ひとつの作品を超えて、オウムについて語る言葉が陥る危険性に対する自戒/他戒であり、そのような無自覚を自己チェックする視点でもある。
A — 鏡像としてのオウムと社会
『A』は、過熱報道も落ち着いてきた1996年3月、某テレビ局のドキュメンタリーとして撮影が開始された。私は、オウムバブルとも呼ばれた95年3月からの報道を、ぼんやりとしか覚えていない。ちょうど公私ともに極限状態に近い日常を送っていたのと、ワイドショーや週刊誌には興味がなかった(これは今も同じだが)からだと思う。そもそもワイドショーや週刊誌によるバッシングは、その社会的制裁という姿勢が嫌いで、スルーが基本姿勢の上に、あれだけの事件を起こしんたんだから仕方ないだろうと、さしてひっかかりもせずに過ぎてしまったのだろう。
それなのに、20年もたってからあらためて気付いたのは、私を含め周囲の友人たちに、オウムに対する拒絶感のみならず、新興宗教だけでなく宗教というものに対する忌避感が根強いことで、これはオウムの事件が落とした陰ではあるにしても、それ以上に、あのときのマスコミ報道によって形作られた、あるいは増幅したものではないのか、ということだった。
ただしマスコミが、視聴率や購買数を稼げるネタに群がるものである以上、そこにはまず私たちの、激しい、収まりのつかない、鎮めることを求める感情の奔流ようなものが存在したことは確かだ。そしてそれを、マスコミに同化して制裁し、精算し、つまり消費してしまったことで、私たちはオウムについて、オウムに対する自らの感情の揺れや流れに対して、それ以上立ち止まって考えることをせず、結果、ただただ拒絶と忌避・嫌悪の残滓を深く心に固着させてしまったのだと思う。
だから、硬く固まったままのものは二つある。オウムとは何だったのか、ということと、私たちの中のどんな部分からオウムは生まれてきたのか、それがオウムバッシングのすさまじさとどういう関係があったのか、ということだ。村上春樹もオウムに関して「無意識の疑問」が解消されていないことを指摘し、それが「後味の悪さ」として残っているという。
あなたは誰か(何か)に対して自我の一定の部分を差し出し、その代価としての「物語」を受け取ってはいないだろうか? 私たちは何らかの制度=システムに対して、人格の一部を預けてしまってはいないだろうか? もしそうだとしたら、その制度はいつかあなたに向かって何らかの「狂気」を要求しないだろうか? ・・・あなたが今持っている物語は、本当にあなたの物語なのだろうか? あなたの見ている夢は本当にあなたの夢なのだろうか? それはいつかとんでもない悪夢に転換していくかもしれない誰か別の人間の夢ではないのか?
私たちがオウム真理教と地下鉄サリン事件に対して不思議な「後味の悪さ」を捨てきれないでいるのは、実はそのような無意識の疑問が、本当には解消されていないからではないだろうか? 私にはそう思えてならないのだ。
(村上春樹『アンダーグラウンド』1997.3.20)
村上の指摘は、前記事の末尾で書いたことに重なる。重要なのは、地下鉄サリン事件から二年後の97年に比べて、今、「誰かの物語」や「別の人間の夢」が確実に、不気味に、増殖しているような感触があることである。それは村上の言う「無意識の疑問」をこの社会がずっと封印してきたことを意味するだけでなく、森達也が暴いてみせたように、この社会がオウムを契機に、大きく(なのに無自覚に)変わってきたことの帰結でもあろう。
オウムは邪悪で、犯罪的で、非人間的で、反社会的で、許されざる存在として、その総体が絶対悪であるとして、マスコミによって「凝縮」された「象徴」的言語で語られていた。これはまた、オウムでないこちらの社会を絶対善と規定するものでもあった。ゆえに、信者たちを内部からドキュメントし、「オウムの中から外を見」ようとする、つまり絶対軸を稼働可能な相対軸に転換する森達也の企画は、カメラクルーと一緒の撮影を二度行った時点で打ちきられることになった。
森は放映のあてもなく、レンタルのカメラを自ら回しながら、仕事の合間に自費で撮影を続ける。別の制作会社や他のTV局にあたってもみたが、軒並み拒絶され、遂にテレビという媒体をあきらめる。この判断は、「オウムの中から見た」外の社会が、「かつて一度も目にしたことのない、剥きだしの表情」をあらわにしていたからでもあった。予想以上の濃度のこれらの光景を、加工や修正をせずそのままテレビで放映することは出来ない。TVディレクターとして、番組が視聴率という宿命から逃れられないことを熟知している森には、自明のことでもあった。「社会への視点」をあきらめればまだ放映の可能性はある。だが、それでは意味がない。「施設の中と外、その光景を当量に見る。その態度を手放すことは、この作品の本質を放棄することと同義なのだ」。
経済的にも時間的にも限界に近く、ぎりぎりの精神状態で模索するなかで、安岡卓司というプロデューサーと出会う。これは森にとってだけでなく、私たちにとっても大きな幸福だった。安岡もまた、「オウムバブル」報道の危うさに早くから気付いていた、数少ないメディア側の一人であった。こうして自主制作のドキュメンタリー映画『A』と『A2』が世に出ることになり、映画監督森達也が誕生した。
『A』は、制作ノートともいうべき書籍版が非常に面白い。森の揺れがオウム広報副部長の荒木浩の揺れに重ねられ、映像ではカットされた部分、背景、後日談など、オウムとオウムをめぐるこの社会が重層的に見えてくる。だが、決して書籍だけで満足してはいけない。やはり映像で、オウム信者たちの姿を見、語る言葉を聞くべきである。そうして、彼らと、彼らに対する周辺住民や、警察や、マスコミの姿を自分の目で見、その言葉にあらためて聞きいるべきである。森の視点によって切り取られたこちら側の姿は、そのまま、自分では見ることが出来なかった、あるいは見たくなかった私(たち)や社会の姿であり、光景なのだ。
映画『A』にはそれを示す衝撃的な場面がある。「転び公防」という、警察が別件で容疑者を逮捕する場合、その容疑を警官が自ら転んで公務執行妨害としてでっち上げるものがあるが、これがオウムの信者に対して行使された。これまでは路地裏など人目の少ないところでなされていた不当逮捕は、この時は白昼の衆人監視の路上で、森がカメラをまわしている目前で行われた。
私服の公安刑事が教団施設から出てきた荒木他二名に、任意による職務質問をする。拒否する山本にまとわりつく刑事は、まるでやくざソックリである。刑事はいきなり山本にのしかかるようにして首を絞め、道路に倒す。即座に自分も転び、膝をさするなどして騒ぐ。ただ自分が転ぶだけでなく、昏倒させるという悪質なものであった。山本はふらふらとした状態のまま逮捕され、パトカーで連れ去られる。
教団は釈放のためにテープの提供を求めた。森と安岡は断る。取材対象に映像を見せることは、作品の中立性の放棄であり、作品の完成や放映をあきらめることになる、との理屈である。荒木らは一旦はそれを承服したものの、なかなか山本が釈放されないことから、弁護士を通して再度テープの供与を求めてきた。森は警察に、不当逮捕であることを目撃した、撮影テープもある、よってただちに釈放するべきである、と綴った手紙を送ったが、無視された。数日後森と安岡は、弁護側と検察側双方に同時にテープを見せる、コピーをとらない、等の条件下に供与を決める。
何をどう取り繕おうが、明らかに冤罪なのだ。口を拭って見過ごすことはできない。当たり前の話だ。・・・オウムがかつて大量殺戮に手を染めたとはいえ、山本康晴が執行猶予付きの有罪判決を過去に受けた人物とはいえ、作品に致命傷を与える可能性があるとはいえ、物事には程度がある。・・・作品は守りたい。しかし守るために、この件に関しては明らかに潔白な一人の市民を犠牲にすることはできない。絶対にできない。
(『A』以下同)
検察はテープを見たとたん、態度を一変させたという。山本は即座に釈放された。だが、驚愕すべきは警察のでっち上げ逮捕の不当さだけではない。
騒ぎを聞きつけたのか、近くの家からわざわざ出てきたステテコ姿に腹巻の親父が、「やっちゃえやっちゃえ」と嬉しそうにしきりに警官に声をかけている。
・・・駆けつけた警官の一人が、路上にうずくまる私服の膝を大声で気遣い、他の警官がやはり不必要なくらい大声で「公防だね?」と傍らの私服に訊ね、問われた警官はこれもまた大声で「ええ、公務執行妨害!」と答える。ステテコ腹巻親父がいいぞいいぞと嬉しそうに笑い、通行人のうち何人かは拍手を送る。・・・
山本を載せたパトカーは発進し、夕闇が色濃い街の雑踏にテールランプがにじんでゆく。ざまあみろバカヤロウとやじ馬の誰かが叫ぶ。死刑にしちゃえ! と誰かが呼応する。現場に取り残された荒木は呆然と立ち尽くしている。ステテコ腹巻親父が事件の証人として同行したらしいと、携帯電話を手にした広末が、上ずった声で荒木浩に報告している。・・・
このステテコ親父が、倒れて意識を失った山本を見下ろしながら、「人間じゃねえんだからよ、こいつら。殺されても文句なんか言えねえんだからよ」と傍らの見物人に嬉しそうに言ったとき、カメラを回しながら、正直僕は殺意に近いほどの衝動を覚えた。これほど人に憎悪を覚えたことは最近ちょっとない。話しかけられた中年サラリーマンは、額の汗を拭きながら歯を剥きだして笑う。「全部死刑にしちまえばいいんだよなあ」と誰かが嬉しそうに親父に同意する。「ポアされて本望だろ」別の誰かが言い、聞いた誰かが大きな笑い声をあげていた。
これが、森の言う「予想以上に濃密な」こちら側の光景である。信者たちに対する罵声や、公安に加勢するやじ馬たちの声や、拍手すら起こっているという異様さに加えて、それをカメラの前で平然と行う警察の異様さがある。カメラがまわっているということは、不当性の証拠を撮られるということだ。民主主義法治国家の警察が、そのことに頓着していないのだ。へたをすれば職を失うばかりか、警察への不信と非難を巻き起こす大変な不祥事に発展するような事例だというのに。
森は後に気付く。刑事たちは森をマスコミの一員と見做していた。マスコミは全面的にオウムの敵であり、警察の味方である。それは周囲のやじ馬たちも同様である。つまりオウムに関しては、マスコミも社会も、どのような人権侵害や不当逮捕であっても例外として許すことを、彼らは知っていたのだ。実際やじ馬の一人は、刑事の「正当性」を偽証しようとパトカーで同行すらしている。許すや見逃すを超えて、これは加担である。
(信者には、図書館の返却日を過ぎただけで逮捕されるなど、常軌を逸した別件逮捕が行われていたことが明かされ)これが法治国家日本の現実だ。戦後半世紀の繁栄を経てたどり着いた民主国家日本の実相だ。しかし今の社会にこの自覚は微塵もない。子供が虫や小動物を無邪気に殺せるように、自覚を失った社会はとめどなく可逆的になる。自覚がないから、昏倒した信者を見下ろして大笑いが出来る。自覚がないから事実を隠し、作り上げた虚構を公正中立だと思い込んで報道することができる。自覚がないから、社会正義という巨大な共同幻想を、これほどに強く信じることができる。
森は「社会正義」という無自覚な残虐性もまた、「洗脳」による思考停止状態にあるからだと指摘する。
(マスコミの一方的なオウムに対する思い込みに対して)僕が抜きんでているのではない。周りが停まっているのだ。「洗脳」という言葉の定義が、情緒を停止させ一方的にしか物事を考えない心理状況を示すのであれば、それは境界線の向こう側だけでなく、こちら側にも同量にある。
・・・
大切なことは洗脳されないことではなく、洗脳されながらどれだけ自分の言葉で考え続けられるかだ。信者たちの思考停止はある意味で事実だ。そして社会の思考停止も同様だ。鏡面を挟んだように、この二つは見事な相似形を描いている。
なぜ地下鉄サリン事件は起きたのか? ずっと抱き続けてきたこの疑問に対しての答えを、ぼくは今何となく思い描くことができる。混雑する地下鉄の車両の中で、幹部信者たちがビニール傘の先端を突き刺した行為の背景を、今はおぼろげながらに推察することができる。情愛を執着として捨象することを説く教義に従い、他者への情感と営みへの想像力を幹部信者たちは停止させた。その意識のメカニズムに組織に従属するメカニズムが交錯し、いくつかの偶然が最悪の形で重なり、その帰結として事件は起きた。しかし情感の否定はオウムの教義にだけ突出した概念ではない。すべての宗教にこの素地はある。その意味では非常に宗教的な空白がこの事件の根幹にはある。同時に「組織への従属」という、特に日本においては実に普遍的なメンタリティも同量にある。
そして被害を受けた日本社会は、事件以降まるでオウムへの報復のように他者への想像力を停止させ、その帰結として生じた空白に憎悪を充てんし続けている。憎悪という感情に凝縮されたルサンチマンを全面的に解放し、被害者や遺族の悲嘆を大義名分に、テレビというお茶の間の祭壇に、加害者という生贄を日々供え続けている。
・・・
彼ら(信者たち)は信仰という空白を自ら選択した。少なくともその自覚を持っている。その空白ゆえの危険性を否定はしない。しかし位相が違うのだ。怖いのは、同じ思考停止状態に陥りながら、その自覚を髪の毛ほども持てない社会の側なのだ。
オウムとこの社会が「鏡像」関係にあることは、複数の人が指摘している。このまま生かしておいたら悪行を行うから殺してもかまわない、というオウムの「ポア」の論理も、路上の民衆に、見事にその自覚なく映し出されている。
『A』は、山形国際ドキュメンタリー映画祭では、それなりの手ごたえを得ることが出来た。観客の不信や拒否感に対する危惧は、プレミア上映の拍手で消えた。だが、マスコミの批評や上映成績は芳しくなかった。映画雑誌のスケジュール表に『A』の上映情報が白紙掲載されるなど、露骨な、これまでにない嫌がらせもあった。マスコミや社会の思考停止をオウム以上に怖いとするこの映画に、当のマスコミや社会がもろ手を挙げて賛辞を送るわけはなかった、のかもしれない。
それでも『A』は国際的には評価され、ベルリン映画祭ではソールドアウトになるほど注目される。その上映後の質疑応答で、日本では耳にしたことのない質問が出た。「これは本当にドキュメンタリーなのか、映画の中のオウムもメディアも警察も市民も、台本にしたがってロールプレイしているようにしか見えない、もしこれが本当というのなら日本とはなんとフェイクな国なのだろう」というものである。
森はこれに対して、組織や集団に対する帰属意識の強い日本独特のメンタリティーは認めつつ、「思考や他者に対する想像力の停止が招く悲劇はどこの国にも起こり得ることではないのか」と返答する。会場ではドイツにも同じ傾向があるという意見も出るが、圧倒的多数は、「これほどグロテスクな思考停止は日本に特有の現象ではないのか」とする意見だった。
まるで日本の恥をさらしにベルリンまで来たような気がして森は落ち込む。彼の重く苦い思いはよくわかる。何故なら「これほどグロテスクな思考停止」は事実であり、それが日本に固有のものではないにしても、日本的な心性と無縁ではないからだ。だが終了後、一人の老婆が歩み寄り、森を抱擁しながら耳元で、「ドイツ人も日本人も、きっと他国の人だって人間はみな同じ。同じだから過去にも戦争が起きたし、これからも起きるのよ。だから大切な問題です。『A』は大切な作品です」と囁く。
老婆の言葉の真実は、ベルリンから三年半後の9.11を契機に、アメリカが全く同じ思考停止から「対テロ」戦争に突っ込んでいったことで証明されてしまった。日本はオウムに、森の提示した複眼的な視点を未だ内面化出来ていない。それは9.11以降の世界もまた同じである。
『A』がクランクアップした97年以降、日本社会はまるで歯止めが外れたように急激に変質した。残虐で動機の不明な犯罪が頻発し、ガイドライン関連法や国旗国歌法、通信傍受法に住民基本台帳改正法など、今後の日本の針路や枠組みに大きな軌道修正を強いる可能性をもつ、数々の法案が、圧倒的な世論を背景にあっさりと成立し、『A』撮影時に一旦は棄却された破防法は、団体規制法(オウム新法)として、より国家統制の色を濃く滲ませながら復活し、タカ派的言動の政治家が熱狂的に支持されて、遂には太平洋戦争における日本のスタンスは正しかったと主張する勢力まで現れた。
全ては地下鉄サリン以降なのだ。
(『A』文庫版、2001年12月のあとがきより)
変質はその後も、秘密保護法、集団的自衛権行使容認から安保法制、憲法改正へ、と続いてきている。根底にあるのは、世論や良識などの衣をまといながらも、その実むき出しになった「他者への憎悪」だと森は言う。確かに、「あと味の悪さ」などというやさやさした形容では語れないほど、私たちは他者に対して、特に少しでも逸脱したり異なったりする他者に対して、不安、不寛容、疑心暗鬼、恐怖、敵対心と排除の欲求を、抱え持ってしまったように思う。そこに「仮想敵」が生まれる。
(つづく)
➾ オウムについて⑤-2 『A』という視点 — A2, A3
A2 — 決して分かり合えない者たちの融和
A3 — 相互作用と善なるものの危うさ

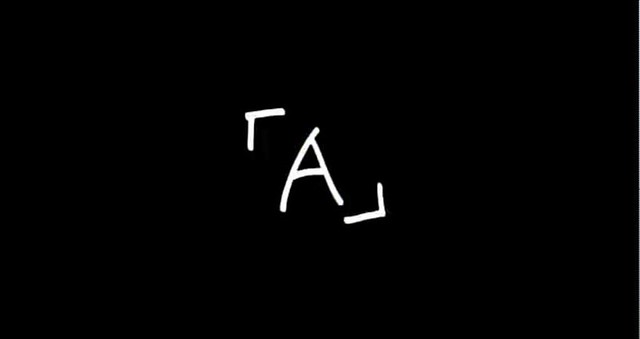









コメント